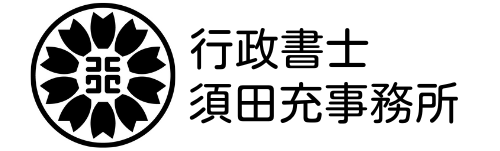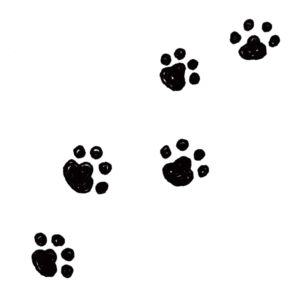『外国資本と農地』太陽光発電事業に係る農地転用の現在地
 再生可能エネルギーの導入が進む中、太陽光発電事業のために農地を取得・転用したいという相談が、全国の自治体や専門職に増え続けています。特に地方における遊休農地や空き家の利活用において、太陽光パネルの設置を想定した土地利用計画は現実味を帯びており、農業振興地域の見直しとも密接に関わっています。
再生可能エネルギーの導入が進む中、太陽光発電事業のために農地を取得・転用したいという相談が、全国の自治体や専門職に増え続けています。特に地方における遊休農地や空き家の利活用において、太陽光パネルの設置を想定した土地利用計画は現実味を帯びており、農業振興地域の見直しとも密接に関わっています。
そんな中、外国人や外国資本による日本国内の不動産取得をめぐる議論が、政治の場でも活発化しています。
国会でも問題提起された「外国資本と土地取得」
令和6年4月、衆議院に提出された【質問主意書 第213回国会 第106号】では、外国人等による土地取得が原子力施設・自衛隊施設・水源地域・国境周辺などの“機微なエリア”にまで及ぶ懸念が示され、国の監視体制に対するさらなる整備が求められました。
現在でも、外為法や重要土地等調査法により、外国人による土地取得について報告義務や調査対象が設けられているものの、「事前規制」の観点ではまだまだ不十分との指摘があります。
こうした状況を踏まえ、「農地」という国家的資源に対して、誰が・どのように・どの目的で使用するのかという点が、これまで以上に問われる時代となりました。
太陽光発電と農地転用の基本構造
農地を太陽光発電用地として使うためには、原則として農地法に基づく「転用許可」または「転用届出」が必要です。
さらに、対象地が農業振興地域内である場合は、「農振除外申出」の手続きから始める必要があります。以下のようなステップが一般的です。
農振除外(該当する場合)
農地転用許可(または届出)
都市計画法・建築基準法・環境関連法令の確認
工事開始前の関係機関協議
これらに加えて、外国人による取得となる場合は、外為法に基づく事後報告手続が必要になるケースもあります。
実務の現場から見える「慎重な審査」と行政書士の役割
農地転用許可は、最終的には県や市町の農業委員会が判断するものですが、実際の審査は“事前協議”の質に大きく左右されます。農業振興課や都市計画課といった関係部署との事前協議をどれだけ丁寧に行うかで、手続きの行方が決まることも珍しくありません。
特に外国人資本による土地取得に関しては、役所側も極めて慎重です。「取得後の土地がどう使われるのか」「資金の流れや背景に不自然な点はないか」など、地域社会への影響も含めて精査されます。
私たち行政書士は、こうした行政側の懸念や責任感を十分に理解しながら、提出する一枚一枚の書類に“地域との信頼”を託すつもりで準備をしています。曖昧な点があれば必ずヒアリングが入り、行政と申請者との間で納得いくまで説明と調整が繰り返されるのが現場の実態です。
制度の「成熟度」に差がある現場では、共に築く姿勢を
また、特に太陽光発電事業においては、市町村によって手続きの経験値に差があります。そのため、行政書士が近隣市町の前例やルールを紹介しながら、役所と一緒に制度運用を考えていく場面も多くあります。
これは「制度を整える側」と「制度を活用する側」が互いに協力し合いながら、地域にとって最適な土地利用のあり方を模索していくプロセスでもあります。
まとめ:土地を売る・買うだけでは終わらない、地域との信頼構築へ
太陽光発電などの再エネ事業は、エネルギー自立や地域防災に貢献する意義ある取り組みです。
しかし一方で、土地利用には厳格な法令や地域ルールが存在し、「やりたい」だけでは進めません。加えて、外国人による土地取得に対する社会的な注目度も高く、関係者すべてが「こんなはずじゃなかった」と思わないような手続きが求められます。
行政書士は、農地法・都市計画法・外為法など複数の法令が交差する現場で、行政と申請者の橋渡し役として大きな責任を担っています。
私たち行政書士須田充事務所では、農地転用や土地取得に関する実務支援を通じて、地域と調和した持続可能なプロジェクトの実現をサポートしています。
個別のご相談はもちろん、企業様向けの出張講義にも対応可能です。どうぞお気軽にご連絡ください。
📞 ご相談・お問い合わせはこちら
📩 gyousei@office-suda.com|📞 052-385-9450
👨💼 行政書士 須田充(愛知県行政書士会所属)