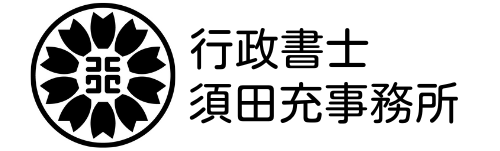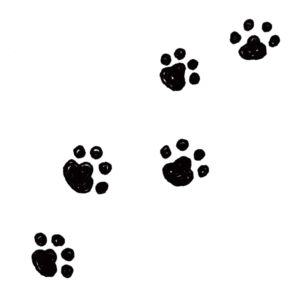その物件、宿泊施設にできる?不動産業者が押さえておきたい“民泊・旅館業”の実務知識
 前回のコラムでは、住宅宿泊事業法(いわゆる「民泊新法」)や旅館業法による宿泊業の仕組みを比較しながら、制度の選択における基本的な考え方をお伝えしました。
前回のコラムでは、住宅宿泊事業法(いわゆる「民泊新法」)や旅館業法による宿泊業の仕組みを比較しながら、制度の選択における基本的な考え方をお伝えしました。
第2弾となる本稿では、「実際に物件をどう宿泊施設にしていくのか」について、不動産実務の視点からもう一歩踏み込んで整理してみます。すでに不動産業に従事されている皆さまに向けた内容となっています。
「宿泊施設にできる物件」とは?
問い合わせが入った中古住宅や空き家、元店舗などを見て「これ宿にできないかな?」と思ったことがある方も多いのではないでしょうか。
しかし、宿泊施設に使えるかどうかは、“建物の用途”や“地域の用途制限”によって大きく左右されます。
たとえば、都市計画法上の「用途地域」によっては、住宅宿泊事業(民泊)や簡易宿所の営業が認められないケースもあります。建物の構造上は使えそうでも、地域制限でNGということも。
また、建築基準法における「用途変更」の要否にも注意が必要です。
「民泊」と「旅館業」、選ばれる物件の違い
簡単に言うと、
👉住宅宿泊事業(民泊)は、“住宅を使った宿泊”であることが前提
👉旅館業(簡易宿所)は、“宿泊施設としての営業”が前提
という位置づけです。
| 項目 | 民泊(住宅宿泊事業) | 旅館業(簡易宿所) |
|---|---|---|
| 主な対象物件 | 住居専用建物 | 店舗・事務所・住宅など幅広く可 |
| 営業可能日数 | 年180日以内 | 制限なし(通年営業可) |
| 許可/届出 | 届出制(住宅宿泊事業法) | 許可制(旅館業法) |
| 要件 | 生活実態、台所・浴室・便所などの設置等 | 客室の広さ、出入口構造、衛生設備など |
つまり、「民泊」は住居系物件向け、「旅館業」は非住居物件や用途変更を前提にした物件に向いている、とも言えます。
なお、民泊のほうが「手軽で簡単」と思われがちですが、実務上は近隣住民への説明責任や、管理者の選任、宿泊者名簿の作成、外国人対応など、やるべきことが意外と多いのも事実です。
許可・届出のポイントは「計画段階の準備」
宿泊施設として物件活用を考えるとき、「とりあえず買ってから考える」のでは手遅れになるケースも少なくありません。
たとえば、
-
用途地域が非該当(宿泊施設不可エリア)
-
建物構造が基準未満(玄関が共用/窓がない/換気設備が不十分など)
-
消防法・建築法の制限(避難経路/火災報知器/用途変更が必要)
など、最初から分かっていれば避けられた問題も多く見られます。
特に、不動産業者として「宿泊施設として売る」「宿泊可能物件として紹介する」場合、適法性の確認はとても重要です。
誤って“営業不可物件”を仲介してしまうと、売主・買主とのトラブルになるリスクも。
不動産提案の幅を広げるチャンスに
空き家や築古物件の提案に「宿泊施設用途」という観点を加えることで、オーナーへの付加価値提案が可能になります。
投資家の視点では、賃貸運用と比較して宿泊業は高収益が見込めるケースもあります。実際に「元・戸建住宅」や「社員寮」「旅館跡地」を簡易宿所として再生した実例も少なくありません。
また、「その物件が宿泊用途に使えるか?」を事前に把握している不動産業者は、他社と比べて説得力と信頼性が増します。
宿泊業の許可申請には多くの法的判断や実務知識が求められますが、行政書士との連携によって、物件紹介の可能性を広げる手助けとなります。
まとめ
民泊・旅館業に関する制度は年々変化しており、行政の運用も地域によって異なります。
そのため、不動産物件を「宿泊施設」として活用するには、制度と実務の両面を把握しておくことが重要です。
「この物件は宿泊施設にできるのか?」といった初期の見極めから、実際の許可・届出手続まで、専門的な知識と判断が求められます。
当事務所では、物件選定時の個別相談はもちろん、企業・団体様向けに宿泊業関連の講義や出張セミナーも対応しております。
制度を正しく理解し、確実に前へ進めたい方は、どうぞお気軽にご相談ください。
📞 ご相談・お問い合わせはこちら
📩 gyousei@office-suda.com|📞 052-385-9450
👨💼 行政書士 須田充(愛知県行政書士会所属)