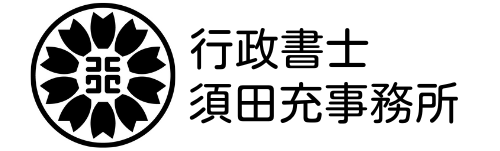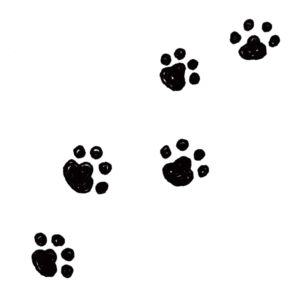『相続土地国庫帰属制度』という新しい選択肢
はじめに
相続した土地をどうするか悩んでいる方が増えています。
遠方で管理できない、農業を継ぐ人がいない、売りたいけど買い手がつかない……。
そんな状況を解決する方法のひとつとして、令和5年4月から始まった 相続土地国庫帰属制度 があります。
制度の概要
この制度は、相続や遺贈によって取得した土地を、一定の条件のもとで国に引き取ってもらえる仕組みです。
申請窓口は全国の法務局。
目的は、増え続ける「所有者不明土地」を防ぎ、地域の管理負担を減らすことにあります。
対象となる土地・対象外の土地
制度の対象となるのは、宅地・農地・山林など幅広い土地です。
しかし、すべての土地が認められるわけではありません。
申請できない土地の例
-
建物が残っている土地
-
抵当権や地役権などの権利が設定されている土地
-
境界が不明確でトラブルになっている土地
-
土壌汚染や産業廃棄物がある土地
-
崖地など、管理に過大な費用がかかる土地
つまり、ある程度整理した状態でないと申請できないケースも多いのです。
現場で耳にする「土地の本音」
なぜこの話題を取り上げようと考えたのかというと、私自身、土地の売買に関わるお仕事をいただく中で感じたことがあるからです。
太陽光発電のために土地を売るケースや、外国人への土地売却などが当たり前に行われるようになった昨今、納得のいかない気持ちを抱えたまま土地を売りに出している方々に出会います。
よくよくお話を伺うと、こんな声が聞かれます。
「土地を持ったまま子供や孫世代が生活できるなら良い。でも現実はそうじゃない。農家を引き継ぐわけじゃないし、外部の人に耕作を頼み続けるほどの余裕もない。土地の管理は大変で維持費もかかる。仕事や結婚で遠方に引っ越せば更に難しくなる。
地元に住み続けるならいいけれど、子供や孫に土地という足かせを残すのは厳しい世の中だ。だからこそ売却して少しでもお金に変えて、次の世代に負担を残さないように今から準備しているんだ。」
このような声を耳にするたびに、「本当に土地を手放す以外の選択肢はないのか?」と考えさせられます。
その答えのひとつが、この 相続土地国庫帰属制度 なのです。
手続きの流れ
-
法務局への事前相談(予約推奨)
-
申請書と必要書類を提出(登記事項証明書、公図、写真など)
-
法務局による審査・現地調査
-
承認/不承認の通知
-
承認後、負担金を納付(原則30日以内)
-
国庫に帰属(国が登記を行う)
費用
-
申請手数料:1筆につき14,000円(不承認でも返金なし)
-
負担金:土地の種類や面積により異なる(概ね「管理費10年分」)
-
宅地や農地 → 20万円~
-
山・森林 → 25万〜60万円超
-
メリットと注意点
メリット
-
管理できない土地を整理できる
-
将来の相続トラブルや税負担を避けられる
注意点
-
すべての土地が対象になるわけではない
-
書類準備や調査に時間がかかる
-
費用がかかる
行政書士ができるサポート
相続土地国庫帰属制度の申請には、登記事項証明書や地籍測量図、公図、相続関係説明図など多数の書類が必要です。
また、土地の境界や権利関係の確認、写真の添付、法務局との事前協議など、専門的な対応が求められます。
行政書士は、以下の点でサポートを行います。
-
必要書類の収集・整理
登記事項証明書、公図、地積測量図、評価証明書などを正確に揃えます。 -
申請書・添付書類の作成
相続関係説明図や申請書類一式を法務省の様式に基づき作成します。 -
境界や権利関係の確認支援
境界に不明点がある場合は、土地家屋調査士などと連携し、申請前に整理を行います。 -
法務局との折衝・相談調整
事前相談の予約や窓口対応をサポートし、必要に応じて補正対応までフォローします。
こうした専門的な手続きを行政書士が代行・補助することで、不備による不承認リスクを抑え、スムーズな申請を実現できます。
まとめ
土地を相続したとき、これまでは「そのまま持ち続ける」か「売却する」かの二択しかないと思われがちでした。
しかし、令和5年から始まった 相続土地国庫帰属制度 によって、第三の選択肢である「国に引き取ってもらう」という道が開かれました。
もちろん、全ての土地が対象になるわけではありませんし、申請には手数料や負担金も必要です。
また、境界の確認や権利関係の整理といった準備が欠かせず、個人での手続きは負担が大きい場合もあります。
それでも、この制度を活用することで、
-
将来の相続トラブルを未然に防ぐ
-
子や孫世代に「管理や税金」という負担を残さない
-
不要な土地を整理し、安心して暮らせる環境を整える
といったメリットを得ることができます。
「残す」か「売る」かに迷ったとき、「国に託す」という選択肢があることを知っているだけで判断の幅は大きく広がります。
土地の相続や処分に悩んでいる方は、ぜひ一度、相続土地国庫帰属制度の活用を検討してみてください。
専門家として、私たち行政書士が書類作成から法務局とのやり取りまでサポートいたします。
📞 ご相談・お問い合わせはこちら
📩 gyousei@office-suda.com|📞 052-385-9450
👨💼 行政書士 須田充(愛知県行政書士会所属)